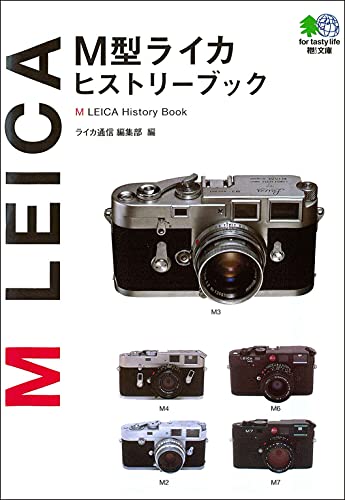お題「思い切ってやめてみた事」
やめてみた事(過去から現在)リストとその感想
タバコ
昭和生まれには宿命といえる喫煙。
それこそ10代の頃から吸っていたわけだが、26歳でキッパリやめた。理由は簡単で、金欠になったこと。当時派遣社員として死に物狂いで毎日を凌いでいたのに、毎月一万円近い金額が、それこそ健康を害するために使われている事実に気がつき唖然とした(気づくのに遅すぎるけど)。お金が絡むと人は真剣になるのか?リバウンドもなくすっぱり辞めることができた。
あれから20年超えた今ももちろん吸っていない。しかし昭和の時代って、法律よりも慣習が優先されていた最後の時代かなと思う。10代で酒タバコなんて、ね?普通といいますか。年上の兄弟がいるともう絶対避けることは無理。 しかし本当にやめて良かった!
お酒
以前ブログにちょこっと書いたが、隣家でボヤ騒ぎがあった時、酔っ払った頭で対応したら犯人疑いされたため、常日頃からシャキッとせねば、と思った。
マルコ福音書13章32節にも、
『いつも起きていなさい、その時がいつ来るか誰にもわからないのだから』 と記されている。
大昔から人は何も変わっていない。
ちなみに今は流石に飲んでいる。しかし体験としては断酒して良かったと思うし、おかげで酒量をコントロールできるようになり、飲まない日が続いてもなんとも思わなくなった。酒量が明らかに減っているので、これは良いこと。最近はドイツの修道院ビールをゆっくり1本味わって飲むのがお気に入り。
コーヒー
コーヒーを飲まないと頭が痛くなる症状が出始めたため、怖くなって飲むのを止めた。
ある日、昼食を摂った後いつもなら習慣的にコーヒーを飲むのだけれど、あまりに忙しくてそのままにしていたら頭痛がしてきた。たまらずにコンビニでコーヒーを買って飲むと、頭痛が治った。なんか、変?
カフェインが切れたから頭痛が起こる、頭痛を治めるためカフェインを摂る、中毒症状そのもの。 だからやめた。ノーマルな身体というかリセットしたかった。
しかしこれは本当に、断酒よりも苦行だった。
特に最初の3日間は頭痛とむくみがひどく、今思い出しても二度とやりたくない。 このようにカフェイン抜き生活は三ヶ月かそこら続いた。スタバでもデカフェ生活。まあ悪くはなかったが、デカフェ飲むくらいなら飲まない方がマシだし、緑茶にもカフェインがあるし、紅茶すら楽しめないのはQOLが下がる。それでいつしか解禁した。
しかし総量としては飲む量が減ったので、例えばそれまでスタバに月数万円近く払っていたのが、半額程度になった。なので、やはりカフェイン抜きも体験できて良かった。
とまあ、以上は過去の出来事で、今はタバコ以外ほどほどに嗜んでいる。次は最近の話。
ネットやめた
いきなり本丸に攻め込んだようなパワーワードだが、すでに1ヶ月になる。しかしこうしてブログを書いたり読んだりしてるんだから矛盾があるので、具体的に何をやめたかリストする。
ネット記事
ダラダラと本当にくだらない記事や射幸心を煽るタイトル、破廉恥な事件の数々に心底うんざりした。そもそもブラウザのスタートページがGoogleニュースだったのでそれを天気に変更。ブラウザ立ち上げる度に今日の天気がすぐに分かって便利。
それで、その生活になってひと月経つが、実際何も変わらない。全く変わらない生活が続いている。ということは世の中のニュースの大半(というかほとんどか)は見なくても知らなくても良い娯楽ということになるのかも。
それからしばらくしてYouTubeなどの動画サイトを観るのもやめてしまった。代わりにアマプラで映画を観る時間が増えた。 とはいえ、私はそもそもフリッカーしかやっていないのでほとんど変化はない。50前にして隠居生活を始めたような感じである。そして大変快適。
先ほどからネット止めても何も変わらないと書いたが、唯一体感できたことが疲労感の減少。例えばこれまで仕事中に何か調べなければならないことがあって、最初は合目的的に資料をネットで調べていたのが、いつの間にかダラダラ波乗り(ネットサーフィン)が始まる現象。
そういうことがなくなったのでやるべき事へ一種のマインドフルネス、コンセントレーションできるようになった。結果、業績が上がった、ということはないのだが、先ほど述べたように疲労度が減った。
これはおそらく毎日情報過多(しかも意味のない内容ばかり)だったものが、入力レベルが森林浴して鳥の声を聞いているほど(言い過ぎかも)に下がったためかと思われる。
まあ、とにかく私はこの生活がかなり気に入ってしまったので、これからも続ける予定。
しかし、Xやインスタ漬けになっている若い人たちはさぞ生きづらいネット社会だろうな、とは思う。
ポイことやめた
ポイ、とはそれっぽいということである。
具体的に挙げるとキリがないが、このイミテーションや高貴なるオマージュという便利な言葉で飾られた”ポイもの”はあらゆる分野に広がっている。
マホガニーのように高級感のある合板、シルクのようなポリエステル、ヤスリで削ったアンティーク風家具、フカヒレのようなこんにゃく(あるのか?)、モンサンクレールシェフ辻口さん監修のコンビニケーキ(実際は作っていない)、フィルムっぽいレタッチされたフィルム写真、などなど。
もちろんこれはポイことが悪いわけではない。あくまで私の贅沢な主観ではあるのだが、50歳近くになるとある程度目や舌が肥えてしまうというか、ポイものはやはりポイものでしかないことが分かってくる(嫌でも分かってしまう)ので、なんだが死ぬ前に、というのも大袈裟だが、本物を見て感じていたいという気持ちが強くなっているのかもしれない。
とはいえ、一体何から手をつけていいのかもわからないので、まずはポジフィルムをルーペで観察(今更か)など如何か。

イライラやめた
これで最後。
生きていると本当にイライラすることが多い。しか国内だけでも自分の他に1億2000万を超える人間がそれぞれの価値観を持って、あくまで法律上のルールに則ってだが、生きているわけだから、日々の生活でも多少の不調和があって当然。
そして何より怒りやイライラは自分を全く幸せにしない。無駄な時間と労力。だから私はそれをやらないことにした。
おかげて最近仏のように穏やかな表情になったとのこと(妻談)
以上、私のやめてみたことリストの紹介でした。










![マディソン郡の橋 [Blu-ray] マディソン郡の橋 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/511zzf0y1kL._SL500_.jpg)











![[BOQ] 保革・保湿・艶出し] オイルケア 3点セット 「タピール レーダーフレーゲ、サフィールノワール スペシャルナッパデリケートクリーム、オリジナルフランネルクロス」レザーケア レザーオイル デリケートクリーム シューケア レザーバッグ レザージャケット お手入れセット [BOQ] 保革・保湿・艶出し] オイルケア 3点セット 「タピール レーダーフレーゲ、サフィールノワール スペシャルナッパデリケートクリーム、オリジナルフランネルクロス」レザーケア レザーオイル デリケートクリーム シューケア レザーバッグ レザージャケット お手入れセット](https://m.media-amazon.com/images/I/41YRFKmfYvL._SL500_.jpg)


















![Pen (ペン) 「特集:【完全保存版】 ライカで撮る理由。」〈2019年3/1号〉 [雑誌] Pen (ペン) 「特集:【完全保存版】 ライカで撮る理由。」〈2019年3/1号〉 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GHLO8fgWL._SL500_.jpg)